第二十一話 CHAPTER7、一夜(2)

「あのね、一人で飲むからそんな、アル中みたいになっちゃうんだよ。落ち込んでたり、辛いときはね、余計に一人で飲んじゃダメなの。ずぶずぶになって、そんな自分にまた嫌気が差して、それを忘れるためにまた飲んでって、繰り返しになっちゃうんだよ……。お酒はね、ひとりで飲むようになったら、精神科を受診しなくちゃダメ。完全にアルコール依存症だからね」
郷原は、あかりと向かい合わせの位置のソファに、身を崩して横たわった。酒瓶を取り上げられてしまったので、一気に体がしんどくなったのだ。
「わかったようなこと言うじゃねぇか……」
「わかってるよ……。だってあたしのお父ちゃん、重度のアル中だったもん」
「……………」
ごくごく薄い、2、3滴しかウィスキーの入っていない水割りが、郷原の眼の前に置かれた。これでは、ただの水と何も変わらない。思いっきり不満そうな顔をする郷原だったが、それとは裏腹に、胸の奥が、あかりに対して、犬のように尻尾を振り始めていた。
「お前の父ちゃん、アル中だったのか」
あかりに心が傾くから、つい、あかりのことを聞いてしまう郷原だった。
「うん。寒いさむぅーい冬の日に、泥酔いして道路で寝ちゃって、凍死した大馬鹿男なの。ほんとロクでもないよ……。ロクでもないけど、そんなにお父ちゃん、寂しかったのかなって……。あたしじゃあお父ちゃんの寂しさ、救ってあげられなかったのかなってさ。今でもそう思うんだ。あたし、あのときまだ高校生だったから」
言いながら、少し涙ぐむあかりであった。恥ずかしそうに、晴れ渡るような力強い微笑みを見せると、人差し指で涙をピッと跳ね飛ばして、ハハハッとおどけて、笑ってみせた。
「そんなわけであたし、郷原さんみたいな男、大嫌い。最低だわ。お酒に逃げるなんて……。最低だけど、放っておけないよなんか……。お父ちゃん、見てるみたいでさ……」
その言葉に、郷原は頬が赤らむのを感じた。自分で、自分をコントロールできない。
「……なぁ……」
こらえられなくて、とうとう郷原は、本当はさっきからずっと言いたかった言葉を、口にしてしまった。
「ん………?」
「ここ来いよ、北山」
「……お金、取るよ?あたしはプロのママだからね」
「……うん……。払う……。ローンでもいい……?」
「うーん、どーしよーかなぁ……。まぁいいや。あたしも、宿泊代払えって言われたら困るから、今日は無料サービスにしてやるよ」
そう言うとあかりは、テーブルの反対側から移動して、郷原が寝そべるソファの胸元に、寄りかかるようにして床へ座った。
あかりの笑顔と視線がぶつかる。こんなとき、何を話したらいいのだろうと考えて、二人ともしばらくの沈黙……。
郷原はふと、久子が不意に席を外して、姉と二人きりになってしまった、この間の見舞いのことを思い出した。
薬のせいで髪が抜け落ち、骸骨みたいになった姉と二人、じっと同じ空気を吸った。あのときの沈黙と、今、このときの沈黙は似ていると郷原は思った。
「あのさ、北山……」
「なに? 郷原さん……」
「お前、きょうだいっている?」
「いないよ。あたし一人っ子だったもん」
「……そっか……」
あかりが、手持ち無沙汰にグラスの淵を撫でていた。
「郷原さんは、きょうだいっているの?」
「まぁな。姉貴がひとり」
「へぇ~……。どんなお姉さん?」
あかりはグラスを撫でながら、郷原の眼をチラリとみた。郷原はじぃっと天井を見ていた。
「……人の顔色ばかり窺う性格をしてる。遠慮ばっかりしていつも損してさ……。要領が悪いんだ」
「そっか……。優しいお姉さんなんだね。きょうだいがいるってうらやましいな。あたしは一人っ子だったから、お姉さんとか妹とか、ずっと欲しかったよ」
郷原は、あかりが作った水みたいな水割りを一口飲んだ。なぜだか口が渇く。胸の奥がじりじりした。
「お前、母親は?」
「いないよ。あたしが中学生のとき死んじゃった」
「……………」
「……でも、お父ちゃんとお婆ちゃんがいたもん。あたしのお父ちゃん、福井の田舎で植木屋やってたんだよ」
「……お前、福井かぁ……。どうりで、なんとなくイントネーションがおかしいと思った。こっちに出てきたのはいつなんだ」
心の奥で、サイレンが鳴っていた。これ以上、あかりについて知るのはやめろと、もう一人の自分が言っていた。それでも、郷原は言葉を止められなかった。
「16歳のときかな。お父ちゃんがのたれ死にしてからすぐ、お父ちゃんの弟にあたる叔父さんが、お婆ちゃんを施設に入れるおカネにするために、福井の家を売っちゃった。あたしはとうとう、家族も、寝るところもなくなって、なんとなくこっちに来たんだよ……。お母ちゃんが死んでから、学校にも馴染めなくてさ、地元に友達もいなかったから、もう福井には居たくなかったの。いっそ一人で、遠くへ行ってみようって……。東京に行ってみたいなぁってさ。そんだけ」
「……………」
郷原は、これと似たような話があったことを思い出していた。年齢はあかりより上だったが、それでも孤独に街をさまよった苦い記憶は、郷原の中にもあった。舞台は、東京ではなく大阪だ。
収容された施設に、その初老の男は面会にきたのである。郷原の兄貴分、川嶋からの紹介だった。川嶋が熱心に通っていた経営研究会の仲間なのだというから、川嶋の顔を立てるために仕方なく会ってやったが――。なんとその男は、郷原が施設を出たら、ぜひ養子にしたいと言ってきた。
(めんどくせぇ――)
どうせ郷原の過去を知り、うわついた気持ちでやってきたのだろうと思い、郷原は男を罵った。どうせひどい暴言を浴びせて、激しく反抗し、自分が手におえない猛獣なのがわかれば老人は、仰天して二度と来ないのに違いない。郷原を気の毒がって近づく大人は、いつもそうすると手のひらを返したようにこの子はダメだと吐き捨てて、帰っていった。
そして自分は、また一つむなしくなるのだ――。世間なんてそんなもの――。どいつもこいつも、嘘ばかり。うわべのきれいごとをいい、内心の欲望を隠したまま、美辞麗句で人をコケにする。誰がそんなものに絡めとられるかっ――!!
しかし、それでも初老の男は、郷原の元に通い続けた。そしてこう言った。
(おめぇ、どこまでも世間が憎いだろう?)
美辞麗句ではない響きを感じて、郷原は初めて顔を上げ、老人を見た。
(それでいい。それで――。幸せなやつら全員、ブチ殺してやりてぇだろ?? な?? 俺もそうさ。この世はバカばっかりだ。どいつもこいつも、テメェの弱さと向きあいもできねぇまま、きれいごとを並べていやがる。それでいい。お前には真実が見えている。この世の真実がな)
「………………」
郷原は初めて、その男を見た。これまで郷原が身を任せてきた大人とは、少し違っていた。男は「雪村幸造」と名乗ると、自分を占い師だと言った。
「しかしよ、俺ぁただの占い師とは違うぜ? これまでお前の近くにいた、きれいごとだらけの宗教家や教師と俺は違う。俺ぁ詐欺師だ。占い詐欺師よ。占いでバカどもからカネを巻き上げ、ざまぁみろと罵ってやる占い師さ。ムショ暮らしの経験もある。どうだ、神に裏切られたお前にはピッタリの身元引受人だろうがよ」
そういって、真っ白い歯と、白髪がかなり混じったグレーの長い髪を後ろで縛っていた雪村は、郷原に屈託ない笑顔を見せた。時期が来て郷原が施設を出ることになり、指定された公民館に雪村を訪ねていくと、雪村は山伏の白装束を着て編み笠をかぶり、にっかりと笑ってみせた。控室の外には、霊能鑑定のチラシを持った連中が並んでいた。
(見てみろ郷原。占いに縋るバカどものこの、欲にまみれた、薄汚い目の色を――!! こいつらは力のある者に縋りさえすれば、自分は死なないと思っている。ガンも難病も治る、カネも入ってくるとな。蹴っ飛ばしてやりたいだろ?? やりたいよな!! 俺も同感だ。だから、巻き上げるのよ、命がきしむほど――。世間を教えてやるのよ、二度と甘い言葉などほざけなくなるほど――。それが俺の占いだ。お前にすべて教えてやる。バカどもを地獄に突き落とす方法をな――!!)
雪村の爺さん――。
でも、無茶な占いが祟って、とうとう仕舞いにゃあ生ゴミになって、大阪湾に沈んじまった――。らしいといえば、らしい最後だった――。
俺が左腕にいつも嵌めている、この金色のロレックス――。雪村の爺さんが殺される直前、嬉しそうに俺にみせてくれた占い賭博の戦利品――。唯一の形見――。
「……その腕時計、ずいぶん型が古いのね」
郷原が急に黙り込んで、ポケットから腕時計を取り出し、じっと見つめていたから、あかりは気になってそれを見た。
「……ああ、これか……。まぁ、ちょっとな。もらいものだから、捨てるに捨てられなくてよ。ずっと使ってる」
「……お父さんから、譲られたものとか?」
あかりが、一段と顔を近づけて郷原を見つめていた。けだるそうに腕に頭を乗せて、じぃっとこちらを見るその顔に、なんとなく異性の魅力を感じて、郷原の頬はわずかに朱色を帯びた。
「そんなんじゃねぇけど……」
「郷原さんの両親は……?」
あかりが、とうとうフェンスを越えてきた。今までだれにも、身の上話などしたことがない。川嶋の内妻、久子以外には――。
「そんなこと、聞いてどうする」
「……別に。ただ、知りたいだけ」
「……………」
郷原は、視線を下へと落とすと、眼を細めた。そんなことをこいつと話して、親しくなって、それでどうなる――? もう二度と、会うこともない女なのに――。そう思って、胸の奥が疼いた。
「話すようなものでもないけど……。親父の記憶はない。俺が生まれる前に死んだらしい。お袋は女手一つで俺たちを育てたが、ある日俺と姉ちゃんを残して、どこかへいなくなった。それだけだ。よくある話さ」
「………そっか……。それでさっき、 “お母さん” って、つぶやいたんだね」
「え……??」
そのひと言に、郷原の顔が一瞬で染まった。耳から首筋まで、茹で蛸みたいに赤くなった。あかりはそれを、もちろん見逃さなかった。
「俺、そんなこと言ってたか??」
「うん。あたしの眼をじぃっと見ちゃってさ……。おかあさんって、つぶやいたよ。すごくかわいかった」
「……………」
郷原は、激しく狼狽して、赤くなったまま固まってしまった。あかりはそれを見てクスクス笑うと、いたずらっぽく人差し指で、郷原の頬を撫でた。少し生えてきた髭が、ぞりぞりとあかりの指の腹をこすった。
「お母さん、そのあと見つからなかったの……?」
「……もういい。その話はしたくない」
「もしかして、怒っちゃった?」
「……………」
郷原は、赤い顔のままじっと黙っていた。あかりはますます、そんな郷原に顔を寄せて、瞳を覗きこもうとした。
「いいじゃん。そんなの、恥ずかしく思うことない。あたし好きだもん、そういう人……。郷原さんのそういうところ……」
「そんなこと、気安く言うなっ!!」
言いかけたあかりの言葉をさえぎるように、郷原が声を荒立てて怒鳴った。あかりはその瞬間、体がびくっと怯えて、指を郷原から離してしまった。
「……………」
「もういい。向こうへ行ってくれ。一人になりたい」
そういって郷原は、この場から出て行くように身を起こすと、ソファから立ち上がろうとした。
「ほ、本当に怒ったの……? ごめんね……。怒ったなら謝るから……。ねぇ……。機嫌直してよ……」
あかりは立ち上がる郷原の胸元にすがった。その媚びるような顔に、また神経が苛立った郷原は、乱暴に力いっぱいあかりの手を振りほどくと、突き飛ばした。
「痛っ!!」
ガシャンと大きな音がして、突き飛ばされたあかりは、ソファの手元に置かれていたサイドテーブルによろけて、背中を打った。その瞬間、あかりが手にしていたグラスが割れた。
それを見て一瞬、郷原の眼に気まずさが走ったが、それでも顔を背けると、さっきまで寝ていたベッドルームのほうへと向かっていった。
背中をさすりながら、それを追いかけるあかりであった。
「ねぇ……。怒ったならごめんね……。そんなつもりじゃないんだよ……。ねぇ、怒らないでよ……」
「うるさいなっ! いいから向こう行けったらっ!!」
猶もすがるあかりを、肩でふりほどいたとき、あかりの髪が逆立った。急に肩をいからせ、拳を握り、白い肌を朱色に染めて、あかりは震える声で絶叫した。
「なによっ!! あんたなんか、あたしだって大っ嫌いよっ!!」
今度はあかりが、郷原を突き飛ばした。よろけて郷原は、ダブルベッドに尻餅をついた。肩の傷に痛みが走る。
あかりは構わずにわめきちらし、手元にあった枕で郷原を叩いた。
「嫌いっ!! そうやってすぐ怒る男なんて、嫌い嫌いっ!! 大っ嫌いっ!! バカっ!! 怖いよっ……! 怖いのっ……! あたしだって、あんたのご機嫌取るので精いっぱいよっ!! ぶったりするなバカっ!!! バカバカっ!!! なんでみんな、あたしのことぶつのよっ……!!」
「…………」
あかりはひとしきりわめいて、枕もシーツもめちゃめちゃにしたあと、呆然とする郷原をよそに、その場にうずくまって泣き出した。
濡れねずみみたいに震えて、自分で自分の肩を抱いていた。その瞬間、郷原には、あかりがひとりぼっち、今までどうやって生きてきたのか、すべて理解できた気がした。
「……ご、ごめん……。ごめん、北山……」
頭に靄がかかって、もう何も計算が働かない。郷原はこんなとき、どうしたらいいのかわからなくて、うずくまったあかりを抱き寄せた。だいっきらいと言われた直後だから、拒絶されるかも知れないと思ったけれど、あかりは無抵抗だった。
「お、俺が悪かった……。泣くなよ……。な?」
「……………」
腕に抱き寄せた瞬間、胸のわだかまりが瞬時に氷解するような、甘い感覚が郷原を支配した。そのまましばらくじっと、あかりを抱いていた。もう先のことなど、どうでもいい――。素直になって、一番あかりに教えて欲しいことを聞こう――。
「なぁ、教えてくれ北山……。お前、娘をなぜ捨てた?」
「……………」
あかりは、郷原の胸から顔を上げて、郷原の眼を見た。
「………捨てたと思う?」
「……………」
「………捨てたと、思うの?」
「……………」
今度はあかりが、涙を眼に溜めたまま、必死で郷原に聞いていた。郷原はその眼を、じっと見つめ返した。
「あたし、りえを産んだ日のこと、絶対忘れない……。ずっと中絶できなくて悩んでたのに、無事に生まれてくれて本当に嬉しかった……。最初のおっぱいを飲ませたとき、信じられないくらい幸せだったよ……。飯田先生の奥さんが、病院にりえを引き取りにきたとき、あたし、やっぱりこの子は自分で育てるって、突っぱねた。そしたら、その一ヵ月後、りえに病気が見つかって……。あたしの生活力ではもう、無理だった……。もう、飯田先生の奥さんに引き取ってもらうしかなかったんだよっ……! えっ、えっ……」
「……そうか……」
郷原は、あかりを抱きしめる腕に力を込めた。左腕が痛いから、片腕でしか抱きしめられないのが残念だった。頬にあかりの艶やかな髪が触れて、柔らかなふくらみが胸に当たるのを感じた。
しばらくじっと、二人抱き合っていたが、やがてあかりが顔を上げた。
「……郷原さん……。なんか体が熱い……。もう休まなきゃ……」
あかりはそういって、郷原から体を離すと、自分がめちゃめちゃにしたシーツや枕をきちんと直して、郷原の手を引いた。
「……ご、ごめんなさい……。これじゃあ、看病にならないね。あたし、郷原さんの上司の方に、面倒みますって約束したのに……」
郷原は、今度はもう嫌がらずに、素直にベッドに入った。
「ああ、あの鬼瓦みたいなオッサンのこと?」
「鬼瓦みたいって……」
「あのオッサンと俺もさ、いろいろあって大変だよ」
郷原は、あかりが差し入れた枕に、ゆっくり頭を乗せながら笑って言った。
「みんな、いろいろあるんだな……」
「まぁね……。みんないろいろあるよ……」
そういって、涙の乾いた顔で、あかりは優しく郷原に笑いかけた。それを見て、郷原も微笑んでいた。
「まだ、看病してくれる?」
「うん」
「じゃあ、俺が眠るまで、ここに居ろよ」
「……うん」
あかりが、郷原を休ませるため、枕元の照明を落とすと、部屋は深海の底のように暗くなった。
闇の中、郷原は手探りで、あかりの手を探していた。今ならぜんぶ熱のせいにして、夢が見られると思った。遠い昔、何度も何度も夢見た、自分だけを撫でてくれる、おかあさんの手――。
あかりの手を見つけた郷原は、そっとそれを握ると、自分の胸に引き寄せて眼を閉じた。熱のせいで頭の芯がとろけそうだった。子どもっぽい男だと思われても、あかりにだったらいい――。

2-のタイトル入れ-300x169.jpg)



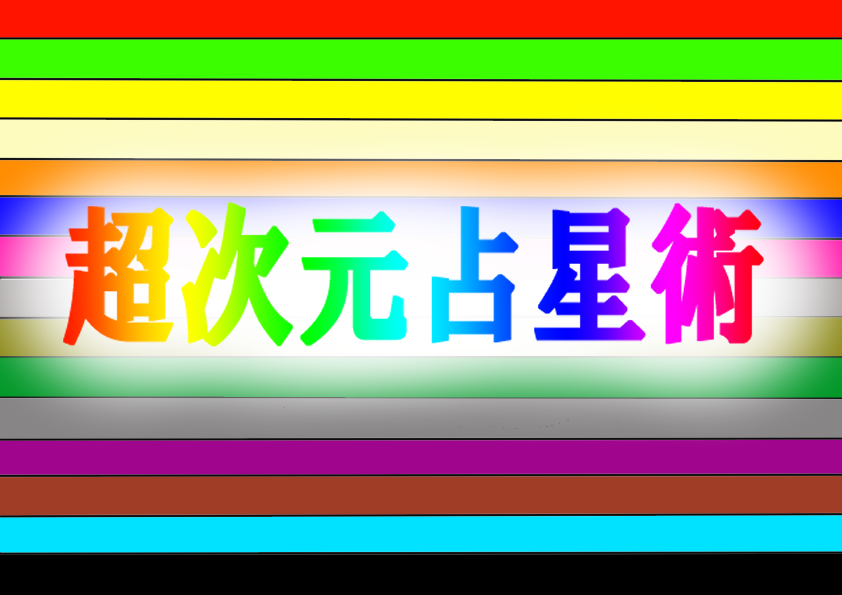
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません